駄音鉢の平鉢や育苗箱、発泡スチロールの魚箱などに、用土を入れ表面を平らにしてから、如雨露などで水をかけます。箸や竹串などで、3〜6cm間隔で穴をあけ挿し穂を差込ます。間隔は葉と葉が触れ合う程度です。さつきなど葉が小さい物は、3cm、葉が大きな樹木は6cmくらいと苗の大きさによって変えます。挿木が終わったら水をタップリ与え用土と苗が密着するようにします。
| 挿し木をする前に、トップジンMまたは、ベンレートとオルトランの混合液を散布し、消毒します。春挿しの場合には、石灰硫黄合剤で消毒します。挿し穂を鋏で切り取った後、カッターナイフなどで切り戻し、半日ほど水に漬けて水揚げをします。用土は、一般に鹿沼土や赤玉土、バーミキュライト、砂など、肥料分や雑菌の少ない用土を使いますが、根が出やすい種類や春挿しをする場合には、畑土でもかまいません。 駄音鉢の平鉢や育苗箱、発泡スチロールの魚箱などに、用土を入れ表面を平らにしてから、如雨露などで水をかけます。箸や竹串などで、3〜6cm間隔で穴をあけ挿し穂を差込ます。間隔は葉と葉が触れ合う程度です。さつきなど葉が小さい物は、3cm、葉が大きな樹木は6cmくらいと苗の大きさによって変えます。挿木が終わったら水をタップリ与え用土と苗が密着するようにします。 |
|
梅雨挿し (新梢挿し) |
6月中旬から7月上旬の梅雨のはじめのころ、今年伸びた新梢を挿します。この時期は、くもりの日が多く、管理が楽です。置き場所は、朝日が1〜2時間くらい当たる場所か、70%くらい遮光した場所に置きます。日中は少ししおれて、朝になるとピンとなるくらい日光が当たる場所が最適です。暗い場所に置くと葉はピンとしていますが、いつまでたっても芽がでません。適度に日光に当てることが重要です。種類にもよりますが、1ヶ月くらいで根が出てきますの、根が伸びてきたら薄い肥料(ハイポネックスの2000倍液)を2週間に1回程度散布します。クチナシやハマボウなど特に根が出やすい樹種を除き植え替えは9月下旬頃にします。百日紅などは、この時期に古枝挿しをすることもあります。 |
|
春挿し |
新芽の出る直前の2月下旬から3月上旬ごろ、去年伸びた枝を挿します。午前中日光の当たる暖かい場所に置きます。春挿しの場合は新芽が出でも根が出ていない場合が多く、植替は早くても6月下旬の梅雨のころになります。 |
|
秋挿し |
10月頃に今年伸びた新梢を挿します。春に挿し木すると病気の出やすいバラ科の植物(ボケ・かりん など)は、この時期が適期です。 |
|
葉挿し |
レックスベゴニアやセントポーリア・弁慶草の仲間など多肉植物は、葉1枚で増やすことが出来る種類が多くあります。(多肉植物でもアロエは、葉ざしでは芽がでません) |
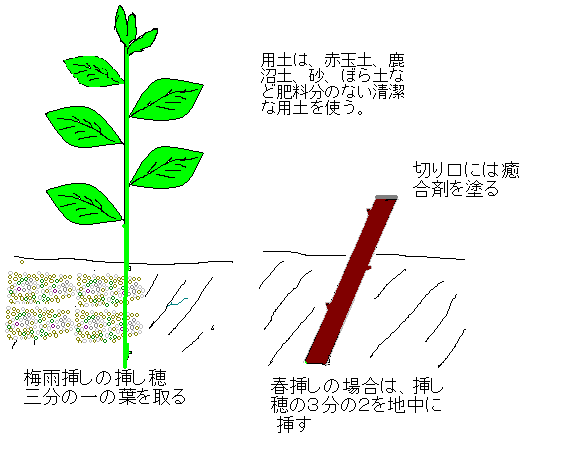
|
常緑樹 |
皐月や椿などの常緑樹の挿し木は、6月の中旬ごろ今年伸びた新梢を挿します。 |
|
落葉樹 |
百日紅や槭などの落葉樹の挿し木は、2月下旬から3月下旬の古枝挿しまたは、6月中旬の新梢挿しもできます。 |
|
多肉植物
|
サボテンやアロエなどの多肉植物を挿し木する場合には、切り口を乾かすことが大事です。挿し穂を切り取った後、1週間ほど陰干し、切り口を乾かしてから砂などに挿します。 |
|
草花 |
草花の挿し芽は、樹木の挿し木にくらべ発根が容易なのものが多く、挿し芽から1ヶ月で植え替えができるようになります。はじめの1週間くらいは日陰におきますが、1週間すると根が出始めますので徐々に日光に当てるようにします。夕方にしおれていても、朝にはピンとなっていれば大丈夫です。あまり日陰に置いておくといつまでたっても根が出ない場合もあります。 |
|
大菊 |
3本仕立ては、4月下旬から5月下旬、苗の芽先5cmくらいの葉の付け根の真下をカッターで切るか、指でポキット折り取る。挿し穂の一番下の葉を取り去り、用土に深さ約2cm・間隔4cmに挿す。一般に団子挿しにする。福助作りは、7月下旬から8月上旬に挿し木する。 挿し芽直後に水をたっぷり掻け、最初の1週間は、直射日光の当たらない場所に置く水は1週間与えない。あまりしおれる場合には、葉水を与える。8日目から徐々に日光に当て始める。15日目には、50%ほどに遮光を減らし、昼間しおれて翌朝ピンとしている程度が良い。約3週間で移植できる程度に発根する。 |
|
五葉松(瑞祥) |
一般に五葉松の挿し木は困難なのですが、瑞祥は、比較的発根が良い品種です。6月20日頃生育の良い新祥を10cm程の長さに鋏で切り取り、下葉の3分の2を取り、日陰で1時間ほど切り口を乾燥させます。カミソリで、1cmほど切り戻し、2時間ほど水揚げをしルートンなどの発根剤を切り口につけてから用土に挿します。 |
|
|
|
| さつきの挿し木 | |
| 時期 | 5月中旬〜6月中旬 |
| 用意する物 | 挿し穂・用土(鹿沼土・ボラ土)・容器(育苗箱・平鉢・魚箱等) |
挿し穂の準備 |
挿し穂は、星の輝など単色花の場合どの枝からとっても良いですが、絞り花の場合は、絞りの花が咲いた枝から出た新芽を挿し穂とします。そうしないと、絞りの品種なのに、単色花だけしか咲かない木になる可能性が高くなります。挿し木をする1〜2日前にオルトランとベンレートの混合液を散布しておくと良いですが風通しの良い場所に置いておけば、農薬は使わなくても良いでしょう。挿し穂の長さは、あまり長くても安定が悪く活着が悪いので、10cm前後の物を選び、はかまと下葉を取り除きます。 |
水揚げ |
整理した挿し穂を品種ごとに輪ゴムなどで軽く縛り、コップなどに入れ1時間ほど水揚げをします。このとき、メネデールの100倍液を使うと発根が促成されると言う意見がある。私も使っていますが、比較実験をしたことないので、効果のほどは定かではありません |
| 発根剤 | ルートンやオキシベロン(インドール酢酸)などの発根剤を使うと効果があります。使い方は、添付の説明書をよく読んでください。発根剤は、使いすぎると、返って発根が悪くなる場合があります。 |
 |
育苗箱などに鹿沼土を入れ水をかけ用土を落ち着けてから、太めの竹串などで2〜3cm間隔の穴をあける。穴の深さは挿し穂の長さの3分の1とする。穴に穂を挿し込み軽く土を押え挿し穂を安定させます。挿し芽が終わったら水をたっぷりかます。 |
管理 |
朝日が2時間くらい当たる場所に置き、3週間ぐらいすれば発根が始まりますので、徐々に日光に当てる時間を長くします。寒冷紗なとを使うと管理がしやすいでしょう。日中は、しおれていても、翌朝には、ピンとなっている状態がよく、あまり日陰に置くと発根が悪くなります。挿し木直後は、水をたっぷりやりますが、後は、やや乾かしぎみにし3〜5日に1回程度潅水し後は、葉水を与えます。3週間くらいから発根が始まるので、ハイポネックスの2000倍液などの薄い液肥を与えます。 私の友人は、建物の東側に挿し芽床を置いて最初から4時間くらい日光が当たる場所に置いています。水を1日に3回くらいやっていますが、100%近く活着しています。(梅雨時ですので毎日日光が当たっている訳ではありません。) |
| 移植 | 順調に行けば、6週間ぐらいで移植できるようになります。育苗箱や平鉢などに6〜7cm間隔植付けます。このころは、真夏なので、風通しの良い涼しい場所に置き、寒冷紗などで、日陰に置きます。直射日光に当てるのは彼岸過ぎてからです。 |
|
ルートン |
説明書 注意事項 |
|
オキシベロン |
有効成分はインドール酢酸。粉末のものと、水に溶かすタイプとある。 |
|
αナフタレン酢酸ナトリウム錠 |
最近はあまり販売されていない。1錠を400CCの水に溶かし(2万倍の水溶液)挿し穂の切口2cmをつけます。草花で約10時間、樹木で、24時間ほどつけてから挿し木します。挿し木をした後の葉面散布でも効果があるといわれます。濃度がすぎると返って発根が遅れますので注意します。 |
| 挿木・挿し芽ができる植物 | |
| 多肉植物 | 葉が厚くて葉に水分を貯蔵していますので、水をやり過ぎない限り簡単に発根します。 |
| 観葉植物 | 熱帯産の観葉植物は、挿木が容易なものが多い。ベンジャミンゴム、ペペロミア |
| 樹木 | 百日紅(サルスベリ)梔子(クチナシ)ハマボウ・さつき・ツバキ・カリン・ブドウ・ブルーベリー・モミジ類・老爺柿・マサキ・ |
| 草花 | コリウス・露クサ類・サルビア・サフィニア・マリーゴールド・菊・ヒャクニチソウ・ |
| TOPへ | 園芸のTOPへ | さつき | ||